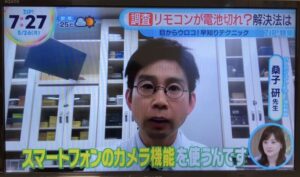土をほるな!? 成功のカギは“ふかふか落ち葉”にあった!ツルグレン装置を使った微生物の観察(中3生物)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
ツルグレン装置で「土の中の世界」をのぞいてみよう
理科室の机の上に、ペットボトルでできた奇妙な装置。その中に詰められているのは、ただの“土”……のはずが、そこから小さな命がぞろぞろと姿を現す瞬間は、生徒たちにとって驚きと感動に満ちた体験になります。
今回は、中学校理科「生物の観察」に関連して、ツルグレン装置を使った微小生物(正確には土壌動物)の抽出実験を行った様子をご紹介します。加えて、授業での実施のポイントや、装置の簡単な手作り方法についても解説します。
■ ツルグレン装置って何?
ツルグレン装置とは、土の中にいる微小な土壌動物を、乾燥と光の刺激で下に追いやって捕まえるための観察装置です。土壌動物は光や乾燥が苦手なため、上から光を当てて乾燥させることで、彼らはより暗く湿った場所(=装置の下部)へと移動します。その下には回収容器を設けておき、そこに動物たちが落ちてくる、という仕組みです。
■ 実際にやってみた
まずは、校庭の片隅からスコップで土を採取。これをツルグレン装置にセットして観察を開始しました。観察倍率は10倍。観察結果がこちらです。


🪲 ゴミムシの観察に成功!
写真やスケッチで記録をとっておくと、分類や考察にもつながります。中学生の観察眼でも見つけられるサイズ感で、生徒の興味を引くにはちょうどよい対象です。

■ 手作り装置にもチャレンジ!
ツルグレン装置は、市販もされていますが、今回は以下のサイトを参考にペットボトルで自作してみました。
👉 お茶の水女子大学サイエンスエデュケーションセンターの紹介ページ
手順(簡単!)
1. ペットボトルを3つのパーツにカット
2. 真ん中部分に網(お茶パックやストッキングでも可)を乗せる
3. 上部に土を入れ、光源(卓上ライトなど)を設置
4. 下部に回収容器としてエタノール入りのカップを設置
これで、お手軽ツルグレン装置の完成です!
ペットボトルを3つに切り分けて、

網を乗せるだけです。

■ 微生物が見えない?原因は「土」にあり!
今回は残念ながら微生物の数は少なめ……原因を調べたところ、「採取した土の種類」が重要であることが分かりました。
👉 参考:i-Field 解説ページ
「スコップで掘り出すような固く乾いた土には、そもそも土壌動物が少ない」とのこと!
正しい採取ポイント:
• 地表の落ち葉が細かくなった堆積層
• そのすぐ下の柔らかく湿った土(手で集められる程度の深さ)
この層には、ダニやトビムシ、ミミズの幼生など、多様な土壌動物が生息しています。
今度はぜひ、この “ふかふかゾーン” を中心に採取して再チャレンジしてみたいと思います!
🧪 授業活用ポイント
• 観察単元(中2:動物の体のつくり)との関連
→ 多様な生物の生息環境と適応の導入にぴったりです。
• グループ活動での探究課題設定にも最適
→ 「どの場所の土が一番多様な生物を含むか」などの比較実験が可能。
• 地域の環境観察活動と連携も視野に入ります。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!