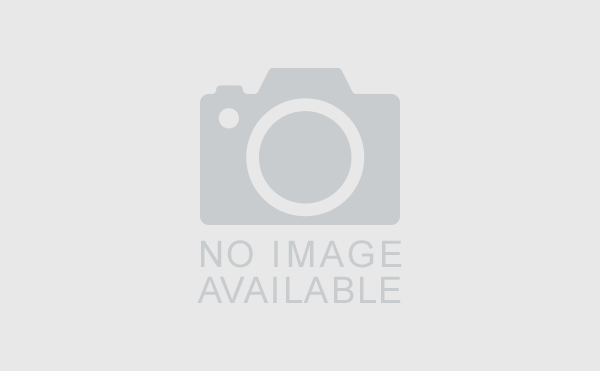ICT利活用の度合いを示すセイマーモデル(SMAR)について
サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。
SMAR(セイマー)モデルについて理科の教育を読んでいて知りました。自分の授業におけるICTの活用モデルとなるので、とてもわかりやすいかなと思います。
SAMRモデルとはフィンランドのプエンテデューラ氏(2010)が考案した、学校現場でのICT活用の程度を示すモデルのことで、以下の英語の頭文字をとった言葉です。
Substitution:代替
Augmentation:拡大
Modification:変容
Redefinition:再定義学研教育みらい.2024.「【夏休みの宿題】家族の一員としての体験を充実させる!探求型宿題を紹介」学研教育みらい.訪問日2024/06/13 https://kyoiku.sho.jp/283368/
例えば代替えは、作文を → ドキュメントで書く というようなもの。従来のペンがPCに置き換わったもので、文具のように使うという例です。
次に拡張は、 → ドキュメントで書くことにより文章構成が速くなる。写真や動画とリンクができるようになる。 というもので、ペンとノートではできなかったことに踏み込んでいくという使い方ですね。
次の 変容 については、 → 共同編集機能を使うことによって、今までできなかった共有をしたり、全員で編集をしたりができるようになる。 というようなコラボレーション機能などの使い方です。
最後に 再定義 については、 → ICTがなければできない授業が生まれる。例えばシミュレーションを使ってデータをとっていくような授業? なのかなと感じています。
授業でPCやタブレットを導入するとき、代替え段階をまず踏んで、生徒や教員が慣れる必要があります。それが分かった上で、変容のフェーズに入って、ああ、便利だな、を感じてもらって、そこからやっと、実際にPCがないとうまくいかない授業の変容や再定義に入っていくという感じで、1や2の段階をふんでおくことがとても大切だなと思っています。