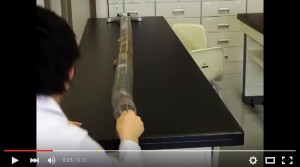日本のトンボ界の王者!昆虫界のトップハンター・オニヤンマの魅力に迫る(オニヤンマの生態)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
先日、群馬県にある峰公園で、その堂々たる姿から「日本のトンボ界の王者」と呼ばれるオニヤンマを、ついに捕まえることができました!全長10cm近くにもなる巨大なトンボが目の前を飛び回る姿は、まさに圧巻。その迫力に思わず息をのんでしまいました。

ナナフシに続いて、今回はこの「王者」オニヤンマの生態と、その驚くべき特徴について、たっぷりとご紹介したいと思います。なぜオニヤンマは「王者」と呼ばれるのか?その秘密を解き明かしながら、きっとあなたもオニヤンマの魅力に引き込まれるはずです。
ただ大きいだけじゃない、昆虫界の食物連鎖の頂点に君臨する獰猛なハンターとしての姿から、環境のバロメーターとしての側面、そして意外な「弱点」を突いた面白い捕獲方法まで、オニヤンマの知られざる世界を一緒に探検してみましょう!
その名は「鬼」に由来
オニヤンマは、日本で最も大きなトンボの一つで、その体長はなんと10cm近くにもなります。黒と黄色の鮮やかなしま模様が特徴的で、この模様が「鬼のふんどし」に似ていることから、その名がついたと言われています。鬼のように大きいからだだからという説もあるそうです。

獰猛な昆虫界のハンター
オニヤンマの成虫は、昆虫界の食物連鎖のトップグループに位置する獰猛なハンターです。ハエ、アブ、ハチ、時にはセミや自分よりも小さいトンボまで、ありとあらゆる昆虫を捕食します。強靭なアゴで獲物を空中で捕らえ、その場で食べてしまう姿は、まさに昆虫界の捕食者そのものです。トンボがハチまで食べてしまうなんて、すごいの一言に尽きますね。
長い幼虫時代と「水質」の関係
成虫の寿命はわずか数ヶ月ですが、幼虫であるヤゴの期間が非常に長く、3年から5年もの間、水中で生活します。この間、ヤゴはミジンコやボウフラ、さらにはメダカやオタマジャクシなどを捕食して成長します。オニヤンマは水質の良いきれいな小川や渓流を好むため、その生息は、その地域の自然環境が健全であることの指標にもなっています。
優れた飛行能力とエメラルドグリーンの複眼
オニヤンマは4枚の翅を巧みに使いこなし、ホバリング(空中停止)や急旋回、バックまでこなす優れた飛行能力を持っています。その最高速度は時速60km以上にも達すると言われており、スズメバチをも上回るスピードで獲物を追い詰めます。また、大きなエメラルドグリーンの複眼は、約2万個もの小さな目が集まってできており、これにより非常に広い視野と優れた動体視力を持ち、わずかな動きも見逃さずに獲物を捕らえることができるのです。

オニヤンマが虫除けになる?

オニヤンマはスズメバチなどの厄介な虫を捕食する天敵であることから、その姿を模したフィギュアが、虫よけグッズとして人気を集めています。私も1つ持っています。これを身につけることで、ハエやアブ、ハチなどが「天敵がいる!」と勘違いし、近寄りにくくなると言われています。我が家でも子どもが身につけていますが、虫たちにとってオニヤンマがどれほど恐ろしい存在であるかを物語っていますね。
虫取り網を使わない「ヤンマ釣り」
縄張り意識の強いオニヤンマの習性を利用したユニークな捕まえ方として、「ヤンマ釣り」というものがあります。これは、小さな石などに糸を付けた仕掛けをオニヤンマの目の前で回すと、縄張りの侵入者と勘違いして襲いかかってくる、というものです。この習性を利用すれば、虫取り網を使わずに捕まえることもできるそうですよ。試したことはないけどやってみたいですね!
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!