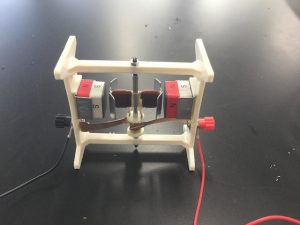おうちがコンサートホールに!たった2つの材料で「ストロー管楽器」を作ろう
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

お子さんと一緒に、何か新しいことに挑戦してみたいけれど、なかなか良いアイデアが思い浮かばない…。そんなお父さん、お母さんに朗報です!今回は、誰でも簡単に、しかもたった2つの身近な材料で、驚くほど面白い「楽器」を作る方法をご紹介します。特別な工具や技術は一切必要ありません。必要なのは、おうちにある「ストロー」と「はさみ」だけ。これだけで、ブーブーとまるでトランペットのような音を出す、不思議な管楽器が作れるのです。
この手作り楽器、ただ楽しいだけでなく、実は「高校物理」の重要な原理が隠されています。フルートやリコーダーといった、いわゆる「管楽器」が音を出す仕組みを、感覚的に理解するのに最適な実験です。音の高さ(音程)を変えるにはどうすればいいのか、音はどのようにして生まれるのか。そんな音の不思議を、遊びながら自然と学ぶことができます。お子さんと一緒に「なぜ?」をたくさん見つけて、理科への興味の扉を開いてみませんか?
【科学のタネ】ストロー管楽器の作り方
さっそく、科学工作の準備を始めましょう!
【用意するもの】
- ストロー
- はさみ
このたった2つで、今すぐにでも楽器作りを始められます。ストローは、100円ショップでも大量に手に入りますし、蛇腹があってもなくてもどちらでも大丈夫です。
驚きの音色!作り方と遊び方
作り方もとてもシンプル。以下の手順で進めてみてください。
① ストローの先を押しつぶす
次の写真のように、ストローの片方を潰してください。
しっかりと潰してください!爪をたてて、ギューっと潰します。だいたい2〜3cmくらいつぶしましょう。

② 潰したストローの先を三角形に切り取る。
次の写真のように、潰した上から2cmくらいハサミで切り落とします。
横から見ると、
横から見たらワニの口のようになっているのがわかります。この長さが大切で2cmくらいはしっかりと切り落とさないと、うまく音がなりません。
これで完成です!簡単ですね。
【遊び方】
切り落とした方を口にくわえて、息を吹き込んでみましょう。うまくいくと、ブーッという音が鳴るはずです。この時、切った部分が細かく震えているのがわかります。この震えこそが、音の正体。息を吹き込むことで、リードが細かく振動し、ストローの中の空気を震わせて音を出しているのです。
【うまく音が出ない時は?】
- つぶし方が甘い
もう一度、ストローの先端をしっかりと強くつぶしてみてください。 - 切り取る部分が短い
先端から2cmはしっかりと切り落としましょう。この長さが、リードの振動に影響します。
音の高さはどうやって変える?
せっかく楽器ができたら、音程を変えて遊びたくなりますよね。実は、このストロー楽器は、管の長さを変えることで音の高さを簡単に調整できます。
音を出しながら、ハサミでストローを少しずつ短く切ってみてください。すると、ストローが短くなるにつれて、音程が少しずつ高くなっていくのがわかるはずです。これは、管の長さが変わることで、ストローの中を振動する空気の波長が変化するためです。
このように、身近なストローを使って、フルートやトランペットと同じ「開管楽器」の仕組みを体験できます。また、クラリネットのような片方が閉じた「閉管楽器」もストローで手作りできますので、ぜひ挑戦してみてください。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!