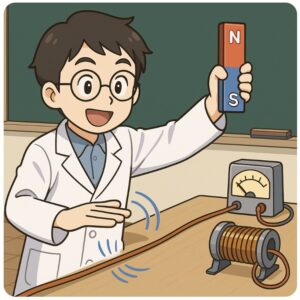化学の基本を実感!酸化銅の質量比から学ぶ「定比例の法則」(一定組成の法則)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
一定組成の法則を体感する――銅の加熱実験で「定比例の法則」に迫る!
中学理科の化学分野で扱う「一定組成の法則(定比例の法則)」は、生徒にとって少し抽象的に感じられる単元の一つです。単なる知識の暗記にとどまらず、実験を通して“質量の比”を体感できる授業設計ができると、学習内容がぐっと生徒の中に根付きます。
そこで今回は、銅粉を加熱して酸化銅を生成し、その質量変化から酸素との一定の割合を読み取らせる実験を行いました。ポイントは、銅の質量を変えても、化合する酸素の割合が一定になることを実感させること。量的な比較をするため、複数の班で初めの銅粉の質量を変えて実験を進める工夫をしました。
実験は教室内で行いましたが、粉末が舞いやすいため、安全対策も重要です。準備と観察のポイント、実験の進め方のコツをご紹介します。
実験の概要と準備
使用する主な材料・器具
• 銅粉(350メッシュ)
• ステンレス皿
• 三脚・三角かさ
• ガスバーナー
• るつぼ鋏
• 電子天秤(2台以上あるとよい)
• 濡れ雑巾
• マスク(粉末対策)
実験方法
1最初に、電子天秤でステンレス皿の質量をはかっておきます。生徒が忘れがちなので注意が必要です。
2. 銅粉の質量を量る
→ 皿をのせた状態で電子天秤を「0」にし、銅粉を量ります。
→ 教卓に銅粉と電子天秤を設置し、2班ずつ測定することで効率アップ。
→ 安全のため、マスクを着用した生徒のみ計量に参加。
→ 10班の場合、0.2g、0.4g、0.6g、0.8g、1.0gの5段階で振り分けました。
3. 銅粉を20分程度加熱する
→ 色の変化を観察しながらじっくりと加熱。時間の確保がポイントです。
→ 途中でかき混ぜると測定誤差につながるため、手を加えないよう指示します。
4. 加熱後、冷却して質量を測定
→ るつぼ鋏で皿を濡れ雑巾の上に移動。手で持てる温度になるまで冷やします。
5. 生成した酸化銅の質量と、化合した酸素の質量を計算
→ 最初の銅の質量との差から、反応した酸素の質量を求めさせます。
観察のポイント
次の画像は熱する前の様子です。

こちらは熱した後の様子です。

途中の様子を動画に撮りました。加熱始めの時に、色が変化していく様子を観察することができます。
• 加熱前の銅粉は赤褐色ですが、酸化が進むにつれて黒っぽい酸化銅に変化します。
• 「銅の質量が2倍になっても、反応した酸素の質量は比例して増えるのか?」といった疑問を持たせておくと、考察が深まります。
• 変化の様子を動画撮影し、他の班の進行と比較するのも有効です。
授業展開のヒント
• 翌時間に、各班のデータを黒板またはスプレッドシートにまとめ、グラフ化して比較。
• 「酸化銅中の銅と酸素の質量比は一定」という一定組成の法則の意味を、実測値と照らして考察。
• 計算ミスや器具操作の誤差を「誤差要因」として振り返る時間も設けると理科的リテラシーが育ちます。
次回は、実際に集まったデータから「化合した酸素と銅の質量比」を分析していきます。生徒の考察がどう深まっていくのか、今から楽しみです!
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。