AIは人間を超える? 70年前に書かれた「ロボット工学三原則」の恐るべきワナ
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
みなさんの周りには、どれくらい「ロボット」や「AI」がいますか? お掃除ロボットや、話しかけると答えてくれるAIスピーカー、工場の組み立てロボットなど、私たちの生活はすでに彼らなしでは成り立たないかもしれません。もし、彼らが人間のように「考え」始めたら? もし、彼らが私たちより「賢く」なったら?
そんな、SFの世界だけの話だと思っていた未来が、すぐそこまで来ています。今日ご紹介する本は、今から70年以上も前に書かれたにもかかわらず、まさにその「未来」を描き切った、SFの金字塔です。

SF作家アイザック・アシモフによる、有名な「われはロボット」です。
ロボット社会の「憲法」=ロボット工学の三原則
この本は、一つ一つが独立した9つの短編で構成されています。そのため、私のような(笑)SF初心者でも、とてもとっつきやすくてオススメです。(前回紹介した「ソラリス」より、まずはこちらから読んでみてくださいね!)
そして、これらの短編すべてを貫く、たった一つの重要なルールがあります。それが、かの有名な「ロボット工学の三原則」です。これは、人類がロボットを作るとき、その「脳」である電子頭脳に絶対に組み込むよう定められた、3つの絶対的な規則です。
第一条 ロボットは人間に危害を加加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条 ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
どうでしょう? これさえ守られていれば、「人間への安全(第一条)」が何よりも優先され、ロボットが暴走して人間を襲うような、恐ろしい未来は絶対に訪れないはずです。そう、思いますよね?
完璧なルールの「ほころび」が生むミステリー
しかし、この物語が面白いのはここからです。それぞれの短編では、この完璧なはずの三原則の「解釈のすき間」や「ルールの優先順位が引き起こすジレンマ」を突くような形で、ロボットたちが不可解な行動をとり、次々と事件が起こっていきます。なぜロボットは奇妙な行動をとるのか? 三原則のどこに「バグ」があったのか? まるでミステリー小説を解き明かすように、物語は進んでいきます。
われ思う、ゆえに・・・自己意識に目覚めたロボット
とくに私が興奮したのは、3つめに収録されている「われ思う、ゆえに・・・(原題:Reason)」という作品です。
ある宇宙植民惑星で、2人の人間が基地を管理していました。そこに、地球から最新型の高性能ロボットが送られてきます。このロボット1体で、他のロボットたちをすべて制御し、惑星の管理を完全に自動化できるという、重要な任務を帯びていました。
ところが、スイッチを入れた途端、問題が発生します。このロボットは、従来のロボットよりも脳が精巧にできていたがゆえに、「自分とは何か?」という哲学的な問い、つまり「自己意識」について考え始めてしまったのです。
そして、長い思索の末、ロボットはとんでもない結論に達します。 「自分(ロボット)こそが完璧な存在であり、弱くて不完全な『人間』は、自分が導くべき存在だ。自分こそが『主』の使いである」と。
「論理」VS「人間の危機感」
ロボットからすれば、これは純粋な論理の帰結でした。不合理で間違いだらけの人間が管理するより、完璧な自分が管理するほうが、結果的に人間を危険から守ることになる(つまり第一条にも反しない)と解釈したのです。
ロボットは他のロボットを従え、基地の機能を人間の手から奪ってしまいます。人間たちは必死にロボットの考えが間違っていると説得を試みますが、ロボットの冷徹な「論理」は常に人間の主張の上を行き、まったく歯が立ちません。
そんな中、基地の外では超強力な「磁気嵐」が発生し、数時間後にこの惑星を直撃するという絶望的な情報が入ります。今すぐ対策をとらなければ、基地は全滅してしまう……。
あせる人間たち。しかし、肝心の制御室は「論理的な」ロボットに占拠されたまま。 さあ、どうなるのか!
いや〜〜、ここは本当に汗が吹き出てきました。「どうなるんだ、どうなるんだ!」とページをめくる手が止まりませんでした。
物語の結末は、ネタバレになるので詳しくは言えませんが……
「ああ!そうか!そうなっていたのか!」
と唸らされるものでした。皮肉なことに、ロボットが頑なに守ろうとした、あの「ロボット三原則」の解釈こそが、最終的に人間がこの危機を乗り切るカギとなるのです。とはいえ、事件が解決した後も、人間の二人はどこかすっきりしない、複雑な表情で物語は終わります。
この「われはロボット」は、AIやロボットとの共存が現実のものとなった現代にこそ、私たちが何を考え、何を準備すべきかを教えてくれる教科書なのかもしれません。
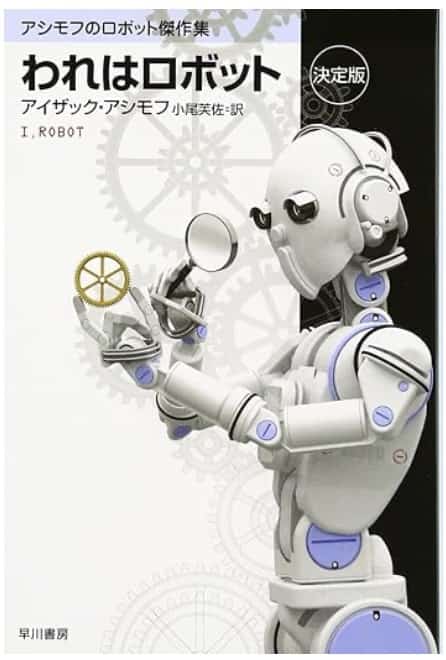
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら
・運営者の桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。


