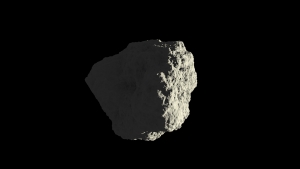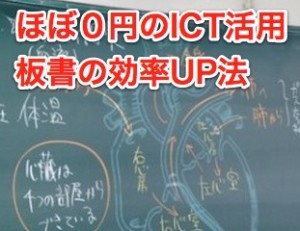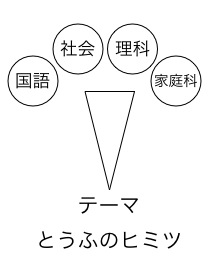『2001年宇宙の旅』機械のほうが人間らしい30年後の未来
機械が人間性を取り入れて、
人間が人間性を失っていく。
SF小説は今読んでも面白い。
「2001年宇宙の旅」を読みました
この小説を読んで、ぼくが中学生のころよんだ国語のテスト評論文を思い出しました。
電車の改札での切符の問題について論じられたものです。
今の生徒にとってみると信じられないかもしれませんが
昔切符は改札で駅員が、はさみのようなもので切って、駅への入退出管理をしていました。
それが機械へととってかわられて、駅員が改札に待機しなくなりました。
(今はもっとすすんでICカードですものね)
その点について述べられていたもので、
駅員が切符をきるという作業は単なる機械的な作業ではなくて、
私達にぬくもりを与えてくれている、
挨拶などを通して人間的な関係を作るための行為でもあったのです。
というようなことが書かれていました。
当初ぼくは、
「何いってんだか!効率的になって人件費が抑制できるんだから、
いいことじゃない」
と思っていたのです。
さて本題!
この本の見せ場、機械VS人間のところについてのみ紹介します。
この小説は、地球からある目的のために木星や土星にいくために、
乗組員が宇宙船にのって向かっているシーンがあります。
宇宙船にはHALという電脳頭脳をもった機械がのっており、
当時のテクノロジーを結集させて作った機械で、
機械なのに、人間の話している言葉を理解することができるように
プログラミングされています。
例えばHALに「気温を◯度下げてくれ」
というと、「了解いたしました。」
などといって気温を下げてくれるといった感じです。
このHALを使いながら、数名の人間がこの宇宙船ですごしており、
主人公は宇宙船のメンテナンスを、他の数名は冬眠のような状態にしており、
活動をしていない状態で寝たままに過ごしています。
主人公は毎日同じ時間におきて、宇宙船に以上がおこっていないか、
HALと確認をして、決まった時間に寝るということを繰り返しています。
そんな中、HALの中に原因は不明ですが、
自我が芽生え始めていきます。
これは開発した地球にいる研究者も考えつかなかったことです。
そして、HALは主人公を含めて恐ろしいことに
乗組員を排除しようとしはじめるのです・・・。
少しHALがおかしいなと思ってきた主人公ですが
確証はもてません。
HALの心理戦がはじまります。
このHALとの戦いが非常に面白かった。怖かった。
主人公(つまり人間)のほうが、実は人間らしくなくなっているんです。
毎朝同じ時間に起きて、タスクをこなし、同じ時間に寝る。
誰とも話しをしない主人公。
テクノロジーに頼りすぎているからかもしれませんが、
主人公のほうがロボットのような生活を送っています。
対してHALの自我はあるいみ人間らしい、嫉妬心?や警戒心をもち
人間を計画的に排除しようとして嘘をついてきたりします。
改札の話しにもどります
今では改札はさらに進化して、ICTカードをかざすだけで通り抜けられるようになりました。
また自動販売機の前にたつと、オススメのものを進めてきたり、
ICカードをかざすとジュースが落ちてきて、声で話しかけてきたりします。
もちろんぼくたちはこのとき無言です。
機械はどんどん人間らしくなっていき、そして私達は人間らしくなくなってきている?
と感じて、なんだか気持ちが悪い感覚になってきました。
iPadで子供を騙らせる
言葉になりませんが、なんとなく。
そんな中次の記事も読みました。
直接はこの記事とは関係ないのですが、
なんとなく気持ちが悪いですよね。
子供をだまらせるためにiPadを渡すってのは。。。
まとまりませんが、2001年宇宙の旅は、アーサーCクラークが1968年、2001年お30年くらいまえに
未来について書いた作品です。
今になっていろいろと考えさせられます。面白い本でした。映画も見てみたいと思います。

決定版 2001年宇宙の旅