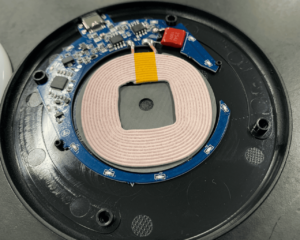理科・国語・社会がコラボ!「とうふのヒミツ」を探る自由な学びの作り方(特別教養講座)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
「特別教養講座」へようこそ!
食卓でおなじみの「お豆腐」が、世界史や科学、江戸時代の料理まで繋がる冒険の扉だったとしたら?今日は、生徒と教師が一緒になって知の探求に出かける、ちょっと特別な学びの場「特別教養講座」をご紹介します。
「特別教養講座」とは、私たちの学校で2006年から続く、教員有志による手作りの学びの場です。学年や教科の垣根を軽々と飛び越えて、生徒と教師が同じ目線で一つのテーマを深掘りしていきます。
長期休暇を利用してユニークなテーマを掲げ、講義や実験、そして学校の外での本物の体験を組み合わせた活動は、いつも新しい発見に満ちています。
今年の春に挑戦したのは、『とうふのヒミツ』。一丁の豆腐から広がる、壮大な世界を巡る冒険です。今回はこの活動を例に、学びの楽しさを無限に広げるコツをご紹介します。
一丁の豆腐から世界を探る!『とうふのヒミツ』
さあ、私たちと一緒に「とうふ」を巡る知的な冒険に出かけましょう!
見学:本物の職人技に触れる
高層ビルが立ち並ぶ東京・神保町。その一角に、今も昔ながらの製法を守る豆腐屋さんが暖簾を掲げています。お店に一歩足を踏み入れると、大豆の甘い香りがふわり。私たちは、店主の方から豆腐作りの哲学を伺い、湯気が立ちのぼる中で大豆が美しい豆腐へと姿を変えていく過程を、食い入るように見つめました。
見学の後には、できたての豆腐や豆乳、そして栄養満点のおからをたくさん購入。これから始まる探求への期待で、足取りも軽くなります。
講義:教科の壁を溶かせ!
学校に戻ると、各教科のスペシャリストである先生たちが、豆腐をテーマに知のバトンをつなぎます。
地理: 「この大豆はどこから来たんだろう?」日本の食卓に並ぶ大豆のほとんどが輸入品である事実から、世界の食料事情や輸送ルートへと話が広がります。
古典: 豆腐のルーツは、なんと奈良時代に遣唐使が伝えたという説が!昔は高級品だった豆腐にまつわる古典文学のエピソードを読み解きます。
生物: 大豆が「畑の肉」と呼ばれるのはなぜ?その秘密は、体を作るもとになるタンパク質。豆腐に含まれるタンパク質の素晴らしさを、分子レベルで探っていきます。
実験:科学の魔法!豆乳が固まる瞬間
ここからは理科教師の出番!豆乳に「にがり」を入れると、とろりとした液体がふるふると固まり、豆腐が生まれます。この現象、実はすごい化学反応なんです。
豆乳に含まれるタンパク質の粒子は、普段はバラバラに漂っています。そこに「にがり」(主成分は塩化マグネシウム MgCl_2)を入れると、にがりの成分が接着剤のような役割を果たし、タンパク質同士をがっちりと結びつけ、立体的な網目構造を作るのです。これが豆腐の正体!
今回は「にがり」の他に、「硫酸カルシウム CaSO_4」など、凝固剤の種類を変えて豆腐作りに挑戦。すると、驚くほど味や食感が変わることを発見! やはり、伝統的なにがりで作った豆腐が、大豆の甘みを一番引き出していて格別でした。
調理:江戸時代の味にタイムスリップ!
探求の締めくくりは、家庭科の調理実習。なんと、江戸時代の料理本に載っていたという 「梨豆腐」 に挑戦しました。豆腐と梨という意外な組み合わせに、生徒たちも興味津々。さらに、豆腐屋さんでいただいたおからを使って、ヘルシーなチョコケーキも作りました。どちらも驚くほどおいしくできて、みんな大満足!
ただの見学旅行じゃない!学びの「化学反応」を起こす秘密
この「特別教養講座」が、単なる社会科見学や校外学習と一味違うのはなぜでしょうか。
複数の教科が組む「知のオーケストラ」
一つのテーマを、様々な専門分野を持つ教師がそれぞれの視点から照らし出す。それがこの講座の最大の特徴です。第一回目の「明暦の大火」では国語・社会・理科が、今回の「とうふのヒミツ」では社会・国語・理科・家庭科がタッグを組みました。これにより、学びが平面的ではなく、立体的で深みのあるものになります。
「好き」の入り口が、たくさんある
文系・理系を問わず、多様な生徒が参加してくれるのも魅力です。「歴史が好き」「料理が好き」「化学実験がしたい」…どんな興味からでも参加できる、学びの入り口の広さがあります。
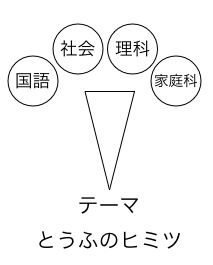
生徒も教師も、みんなが「探究者」
この講座は、やりたい教師が自主的に企画し、参加したい生徒が自分の意志で集まります。そこにあるのは「教える-教えられる」という関係ではなく、共に学ぶフラットな関係です。教師も自分の専門外のテーマについて必死に勉強し、生徒の前で発表します。他教科の先生の講義は、私たちにとっても刺激的! 生徒と一緒になって「へぇ〜!」「面白いね!」と声を上げ、知的好奇心を共有する時間は、何物にも代えがたい喜びです。
点と点が繋がり、新しい「好き」が生まれる
参加したIさんは、「一つの物事を、いろんな角度から見られるようになった」と語ってくれました。理科が好きな生徒が、豆腐の歴史を知って古典の世界に興味を持つ。国語が得意な生徒が、タンパク質の凝固という化学反応の美しさに感動する。そんな素敵な「化学反応」が、あちこちで起こります。そして面白いことに、それは生徒だけでなく、私たち教師の間でも起こるのです。知識と経験が繋がる快感は、次の講座への大きな原動力になります。
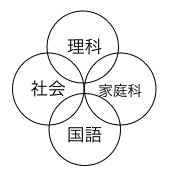
予想外のゴールにたどり着く冒険
私たちが当初設定したゴールよりも、ずっと深く、ずっと面白い場所へ生徒がたどり着くことがよくあります。それぞれの興味を起点に学びを広げ、自分だけの深さで物事を追求していく。その姿は、私たちが想像もしなかった輝きを放ちます。これこそが、この講座の醍醐味なのです。

あなたの学校でも!「特別教養講座」を始める3つのコツ
このワクワクするような学びを、もっと多くの場所で実現してほしい。そんな思いから、私たちが見つけた成功のコツを3つ、ご紹介します。
「やりたい人、この指とまれ!」で始める
最も大切なのは、教師も生徒も「自由参加」であること。「何か面白いことやらない?」と、まずは身近な先生に声をかける。その小さな好奇心の種火から、静かに始めていくのが長続きの秘訣です。私たちもそうして始まり、今では学校全体が応援してくれる取り組みに成長しました。
先生も「学び手」になる時間を作る
単なる見学で終わらせないために、教師自身がテーマについて学び、生徒の前で講義をする時間を少しでも設けましょう。たとえ1人10分でも構いません。身近な先生が熱意をもって語る言葉は、生徒の心に深く響き、体験をより豊かな学びに変えてくれます。
「インプット→アウトプット」の黄金パターン
これは経験から見えてきたことですが、1日目に講義やグループワークで知識をインプットし、2日目に校外学習で体験(アウトプット)するという流れが、学びの効果を最大化するようです。事前に視点を持つことで、現場での発見が何倍にも面白くなります。
この取り組みが、皆さんの学校や地域での新しい学びのヒントになれば嬉しいです。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!