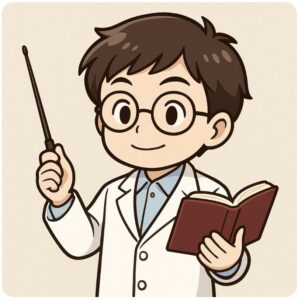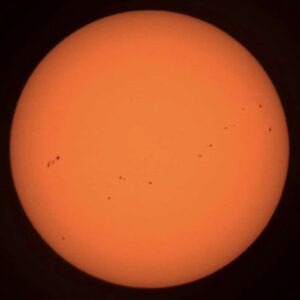物理で未来予知?たった1つの公式でわかる「等加速度運動」のすごい世界
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
もし、未来や過去のことがわかる「魔法の呪文」があるとしたら、知りたくありませんか?実は、それにとてもよく似たものが、高校の物理の教科書に載っているんです。それは一見すると、ただの長くて難しそうな数式。でも、その本当の姿は、ボールの落下から潜水艦の航行まで、あらゆる物体の動きをピタリと予測できてしまう、超強力なツールなのです。今回は、そんな物理の世界の「魔法の呪文」、等加速度運動の公式の秘密を一緒に解き明かしていきましょう!
未来と過去を解き明かす
<位置の公式>\[x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0\]
<速度の公式>\[v = at + v_0\]
x:位置 a:加速度 t:時間 v_0:初速度 v:速度
これがその呪文です。高校物理で最初に登場する公式の中でも特に長いため、これを見ただけで「うっ…」と物理が苦手になってしまった人も多いかもしれませんね。でも、安心してください。この公式は、運動の様子をイメージできれば全く怖くありません。たくさんの文字が出てきて混乱しそうですが、物語の登場人物だと思って整理してみましょう。
x (位置): v (速度): 物語の主人公。時間と共に場所や速さが変わります。
t (時間): 物語の舞台装置。時間が進むことで物語が展開します。
a (加速度) : v_0 (初速度): 主人公の初期設定。どんな速さでスタートし、どんな力が加わり続けるかを決める重要なパラメータです。
つまり、この2つの公式が言っているのは、「時間(t)が経つと、物体の位置(x)や速度(v)がどう変化するのか」という、とてもシンプルなことなのです。例えば、マンションのベランダからボールをそっと落とす場面を想像してください。地球上では、物体は重力によって9.8 {m/s^2}という一定の加速度で落下します。この値を a に、「そっと手を離した」ので初速度 v_0 には0を代入してみましょう。
この式の時間 t に「1秒後、2秒後…」と未来の時間を代入すれば、その瞬間の落下距離がピタリと予測できます。
t=0[s] のとき x=0[m]
t=1[s] のとき x=4.9[m]
t=2[s] のとき x=19.6[m]
t=3[s] のとき x=44.1[m]
逆に、ボールが地面に落ちるまでの時間を測れば、この式を使ってベランダの高さを知ることもできます。まさに、未来も過去もわかる便利な式ですね!
公式は作れる!グラフで見る運動の世界
ところで、こんなに便利な公式は、一体どうやって作られたのでしょうか?その秘密は、「v-tグラフ」という、速度と時間の関係を表すグラフに隠されています。
台車を坂道で走らせる実験を想像してみてください。坂道ではどんどんスピードが上がり(等加速度運動)、平らな道では同じ速さで進み続けます(等速直線運動)。この様子をグラフにすると、次のようになります。
科学者たちは、このグラフを眺めているうちに、驚くべき法則を発見しました。なんと、グラフと横軸で囲まれた部分の「面積」が、物体が移動した「距離」と全く同じになるのです!
この発見を使えば、公式を自分たちの手で作り出すことができます。
例えば、速度0からスタートして、一定の加速度 a で加速していく運動を考えましょう。t 秒後の速度は at になるので、グラフはシンプルな三角形になります。
三角形の面積は「底辺 × 高さ ÷ 2」ですから、移動距離 x は…
\[x = t \times at \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}at^2\]
見覚えのある形が出てきましたね!では、初めに速さ v_0 を持っていた場合はどうでしょう?今度はグラフが台形になります。この面積は、下の長方形と上の三角形に分けて計算できます。
x = (三角形の面積) + (長方形の面積)
\[x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t\]
これで、あの長かった「位置の公式」が完成しました!公式はただ暗記するものではなく、具体的なイメージから導き出せる、ということがわかると、物理は一気に面白くなりますよ。
公式で世界をのぞいてみよう!
この公式は、私たちの身の回りの様々な現象や、最先端の技術にも応用されています。
■潜水艦は目隠しで海を進む?
GPSの電波が届かない海の奥深く。潜水艦はどうやって自分の位置を知るのでしょうか?ここで活躍するのが、加速度を測る「加速度計」です。測った加速度 a をもとに速度 v を計算し、v-tグラフの面積から移動距離 x を割り出す…まさに、等加速度運動の公式をリアルタイムで使い続けているのです。この「慣性航法」という技術は、宇宙船などにも使われる、まさに最先端の知恵なのです。
■雨粒が凶器にならないのはナゼ?
もし空気がなかったら、上空1kmから降ってくる雨粒は、地上に着く頃には時速500kmを超える弾丸のようなスピードになります。計算してみましょう。
まず、落下時間を求めます。
約14秒で落下してきます。次に、その時の速度を計算すると…
秒速140m、これは新幹線よりもずっと速いスピードです!
しかし、現実にはそうなっていません。それは、私たちを包む「空気抵抗」が存在するからです。空気の粒がブレーキをかけることで、雨粒のスピードは安全な速さに保たれています。空気は、私たち生物を宇宙からの小さな隕石や、高速の雨粒から守ってくれる、見えないバリアの役割も果たしてくれているのですね。
物理の世界の共通言語「単位」
最後に、物理の世界で欠かせないルール、「単位」についてお話しします。
速度の m/s(メートル毎秒)や加速度の m/s2(メートル毎秒毎秒)など、物理では様々な単位が出てきます。これらは 「国際単位系(SI)」 とよばれる世界共通のルールで、世界中の科学者が同じ土俵で話すための大切な言語です。
ところで、なぜ加速度の単位は秒が2乗(s2)になっているのでしょうか?
それは、加速度が「1秒あたりに、どれだけ速度が変化するか」を表す量だからです。「速度(m/s)」の変化量を、さらに「時間(s)」で割るので、
(m/s) ÷ s = m/s2
となるわけです。
物理の世界では、この「単位」を意識することが非常に重要です。単位が違うもの同士は足し算ができない(例:1cm + 2kg は意味不明)など、単位は計算の正しさをチェックする道しるべにもなってくれます。公式を正しく使いこなし、身の回りの世界の謎を解き明かすために、ぜひこの「単位」という言語にも親しんでみてくださいね。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。