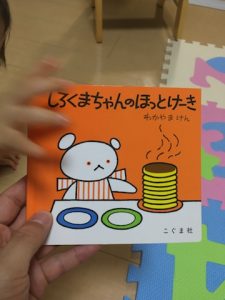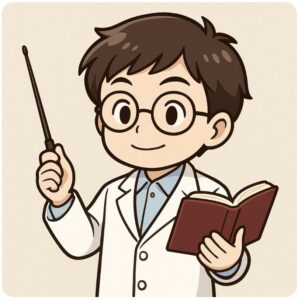カタカタアヒルに隠された科学!子どもの安全を守るカム構造の秘密
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

レトロなおもちゃ発見!なんとぼくが生まれたときに使っていたものだそうです。
子どもの頃に遊んだおもちゃには、どんな秘密が隠されているか考えたことはありますか?ただ楽しいだけでなく、そこには科学の知恵や、使う人のことを考えた工夫が詰まっています。今回、実家で偶然見つけたレトロなアヒルのおもちゃをきっかけに、その巧妙な仕掛けをひも解いていきましょう。
これは、手で押すとアヒルがカタカタと動く、昔ながらの子供用のおもちゃです。子どもの頃の記憶を呼び起こしながら眺めていると、いったいどうやって動いているのだろうと好奇心がわいてきて、思わずひっくり返してみました。
すると、そこには中学校の技術の授業で習った 「カム構造」 が使われているのがはっきりと見えました。カム構造とは、回転運動を上下や左右の直線運動に変える機械的な仕組みです。このおもちゃでは、車輪が回ると、中心からずれた部分に取り付けられた突起(カム)が、アヒルの足につながる棒を押したり離したりすることで、カタカタとユーモラスに動く仕掛けになっていたのです。


時計回りに回したときは、棒がひっかかりアヒルがうごきます
カム構造が使われていることは予想通りでしたが、このおもちゃの本当のすごさは、 「逆回転防止」 の工夫にありました。アヒルの足につながった棒が、逆向きに回そうとするとカムのくぼみに引っかかり、回転を止めるストッパーの役割を果たしていたのです。

反時計回りに回そうとすると、棒がひっかかりってストッパーになります。逆回転防止となります。
この「逆回転防止」の機能は、子どもの安全を守るための、非常に考えられた設計です。子どもが夢中になっておもちゃを押しているときに、うっかり引いてしまっても、後ろに下がることがないので、つまずいて転んでしまう危険を減らすことができます。アヒルがカタカタと鳴る音は、単に子どもを喜ばせるためだと思っていましたが、実はこの逆回転防止の仕組みと連動していたとは驚きです。
ジャイロコマなど、昔から愛されてきたおもちゃには、見た目の楽しさだけでなく、このようなシンプルで奥深い科学的な工夫がたくさん詰まっています。それはまるで、おもちゃという小さな世界に閉じ込められた、偉大な発明家たちの知恵の結晶のようです。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!