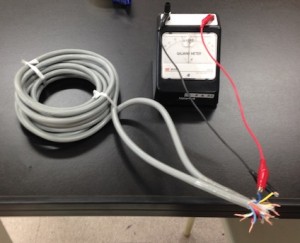なぜ光が揺れる?おしゃれなランプに隠された「フレミング左手の法則」(バイブラランプ)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
皆さんは、カフェやレストランでおしゃれな照明を見たことがありますか?先日、水道橋駅の近くにあるインテリアショップに入ったとき、とても面白い電球に出会いました。まるでろうそくの炎のように、電球の中の光がゆらゆらと揺れているのです。
あまりに面白いので、お店の方に許可をもらって撮影し、調べてみたところ、「バイブラランプ」という名前で売られていました。

フィラメント(光る部分)がゆらゆら揺れて、それによって照らされた壁の影もゆらゆらと揺れる、とても雰囲気のあるランプです。
なぜランプは「揺れる」のか?
なぜこのランプのフィラメントはゆれているのでしょうか。 動画や写真をよく見てみると、揺れているフィラメントの根元に、黒いものがついています。これは一体何でしょうか。

実は、この黒いものの正体は磁石だったんですね。「電気」と「磁石」とくれば、理科の授業を思い出しませんか? そう、中学で習う「フレミング左手の法則」です。「電・磁・力(でん・じ・りょく)」と覚えた方もいるかもしれません。
磁石がある場所(=磁場)で電気を流すと、そこに「力」が発生します。モーターが回る原理と同じですね。
このバイブラランプがただの電球と違うのは、この「力」をうまく利用している点です。
フィラメントの根元に磁石がセットされています。フィラメントに家庭用の交流が流れます。「電気」と「磁石」がそろうので、「力」が発生してフィラメントが動きます。ここで重要なのが、流れる電気が「交流」だということです。 交流は、電気が流れる向きが1秒間に何十回もリズミカルに入れ替わります。電気が「行ったり来たり」しているイメージです。
電流の向きが入れ替われば、「フレミング左手の法則」によって発生する「力」の向きも、同じリズムで入れ替わります。 その結果、フィラメントはまるでダンスするように、ゆらゆらと「振動」を始めるのです。
まさに、交流をうまく利用した、科学的で、おしゃれなランプですね!
「振動」は身近なところで大活躍!
この「交流の振動」を利用した製品は、他にもたくさんあります。 例えば、熱帯魚や金魚を飼うときに使う「エアーポンプ(水槽のブクブク)」です。エアーポンプも、中にはコイル(電磁石)と永久磁石が入っています。 交流が流れると、コイルが作る磁場の向きがリズミカルに変化し、永久磁石が振動します。その振動がポンプの膜を動かして、空気を送り出す流れが生まれるのです。
学校で使う「アレ」も振動仲間
学校の理科室で見たことがあるものといえば、「記録タイマー」も交流を利用しています。台車の運動を記録するときに使う、あのカチカチと点を打つ機械です。 あれは、家庭用の交流が持つ「一定のリズム(周波数)」をそのまま利用しています。
例えば東日本の場合は電源周波数が50Hz(ヘルツ)なので、1秒間に50回振動します。西日本なら60Hzなので1秒間に60回。この正確なリズムで点を打つことで、物体の速さの変化を調べることができるのです。
交流は、精密機器などではそのまま利用するとうまく動作しないことも多くありますが、バイブラランプやエアーポンプのように、あえてこの「振動」という性質を逆手にとったユニークな製品もたくさんあります。
皆さんもぜひ、身の回りで「振動している電気製品」を探してみてください!
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら
・運営者の桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!