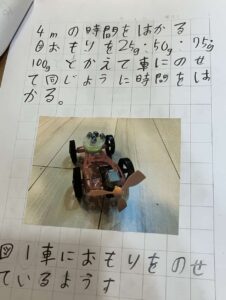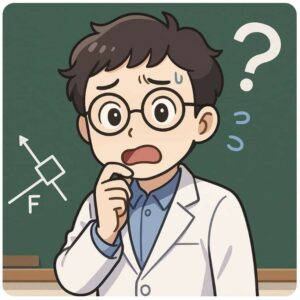金沢21世紀美術館で科学体験!色の三原色で世界が変わる魔法の家(カラー・アクティヴィティ・ハウス)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
先日、金沢21世紀美術館に行ってきました。数ある魅力的な作品の中で、特に私の心を掴んで離さなかったのが、オラファー・エリアソンさんの《Colour activity house(カラー・アクティヴィティ・ハウス)》という作品です。

この作品は、理科教師の視点から見ても非常に興味深く、子どもたちの学びにとって素晴らしいきっかけになると感じました。一見すると、ただ美しいカラフルなガラスの壁でできた迷路のように思えるかもしれません。しかし、そこには光と色の不思議な科学が隠されているのです。
シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)という、私たちが「色の三原色」として学ぶ3つの鮮やかな色ガラスの壁でできています。これらの壁が渦巻き状に配置されているため、鑑賞者はその中を歩き回りながら、さまざまな色の光を体験することになります。

外から差し込む太陽の光、そして作品の中心にある光源。これらの光が、色のついたガラスを通り抜けることで、私たちの目に届く光の色が変化します。たとえば、シアンのガラスを通してイエローのガラスの影を見ると、そこには緑色の世界が広がります。

これは、光がガラスを透過するたびに、特定の色だけが吸収されることによって起こる現象です。
この仕組みは、印刷などで使われる「減法混色」の原理ですね。絵の具を混ぜて色を作るのと同じように、色ガラスを重ねることで、光がどんどん吸収され、最終的に黒に近づいていくのです。
子どもたちは、この作品の中を無邪気に走り回っていました。その光景は、ただ楽しんでいるだけでなく、無意識のうちに色の変化という不思議な現象を体で感じ取っているようでした。「どうして色が変わるんだろう?」という素朴な疑問は、やがて光や色、そして科学への興味へとつながっていくことでしょう。いつか、理科の授業で「色の三原色」を習ったとき、このカラフルな体験を思い出してくれたら、こんなに嬉しいことはありません。こちらは公式サイトの映像です。
次は手作りでCMYキューブを作ってみましょう。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!