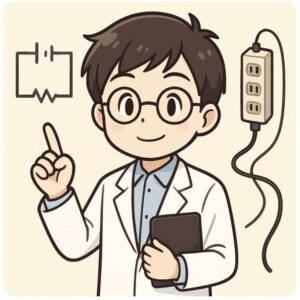「探究」はなぜ必要なのか?ふと立ち止まって考えたい・探究学習の二つの意味
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
私たち理科教師の仕事は、外から見れば、好きな実験をしたり、子どもたちに理科の面白さを伝えたりと、とても自由に映るかもしれません。しかし、その内側には、授業の進度、受験対策、保護者の期待といった、さまざまなプレッシャーが渦巻いていることを、日々痛感されている先生方も多いのが実情です。
特に先日講演に行ってきましたが、高校では、膨大な授業内容をこなしながら、どうにかして実験の時間を確保しようと頭を悩ませる。私自身、高校教師を15年間務めていたので、その葛藤は本当によくわかります。さらに、「もっと受験対策をしてほしい」という要望に押され、探究的な活動が削られて、問題演習中心の授業になってしまう…。理想と現実の狭間で、日々もがきながら教壇に立っている先生方は少なくないはずです。私も実際に同じ悩みを抱えながら、時間を見つけては実験を開発していました。
そんな中、文部科学省からは「探究を大切に」というメッセージが繰り返し発信されています。高校では探究科目が新設されるなど、教育現場全体が探究を推進する流れにあります。しかし、日々の多忙な業務に追われる中で、「またやることが増えた…」と、心の中でため息をついている先生もいらっしゃるかもしれません。
ここで一度、立ち止まって考えてみたいのは、「お上から言われたから探究をやる」という受け身の姿勢では、その教育効果が半減してしまうということです。私たち教師自身が、探究の意味、そしてなぜ今それが求められているのかを深く理解し、自分の言葉で腹落ちさせておくこと。これが何よりも大切だと考えます。そうでなければ、探究の時間が単なる「実験の時間」や「作業の時間」になってしまい、生徒たちも「一体何をやらされているんだろう?」と目的を見失ってしまうかもしれません。
先日、私たちの学校の理科部会でも「探究の意味」について議論しました。先生方それぞれの意見があり、簡単にまとまるものではありませんでしたが、それでいいのだと思います。大切なのは、自分なりの探究の意義を見つけることです。
そんな中でも、多くの先生が一致していたのは、「探究こそが、主体的・対話的で深い学びを最も効率よく実現する方法だ」という点でした。生徒が自ら手を伸ばし、自らの力で知識を獲得する経験こそが、知識の定着を飛躍的に高めます。その意味で、「主体的・対話的で深い学び」は、単なるスローガンではなく、非常に効率的な学びの方法論の一つと言えるでしょう。
また、探究にはもう一つ、非常に重要な意味があると考えています。ここに書いていある全てが私個人の意見ということをご了承いただきたいとおもいますが、社会に出れば、教科書に答えが載っていない「答えのない課題」に直面することが多くなります。そのような時、ただ戸惑って立ち尽くすのではなく、「どうすれば解決できるか」を自ら考え、行動に移せる力が必要です。このときに思考のフレームワークとして機能するのが「探究の過程」です。
探究活動は、この思考プロセスと行動力を、学校という安全な場所でじっくりと体験するための貴重な場です。つまり、探究活動は次の2つの役割を担っていると言えます。
- 理科の知識・技能を効率よく教える役割: 生徒が自ら手を伸ばして知識を掴む経験を通して、深い理解と定着を図る。
- 探究そのものを教える役割: 答えのない課題に立ち向かうための思考のフレームワークを、日々の授業や自由研究を通して体験的に学ばせる。
学校の先生は単に知識・技能を教えていればいいということではないということがよくわかります。塾や保護者の方には、こうした探究の真の価値が伝わりにくく、また保護者の方は何をやっているのかと焦りを感じることもあるかもしれません。しかし、これこそが、次世代を育てる立場である私たち理科教師が大切にすべき部分だと信じています。教師は1だけではなく2も教えるということから、多忙で・忙しくて・大変ではあるものの、重要なことで・やりがいのある仕事になっているのかなと思います。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!