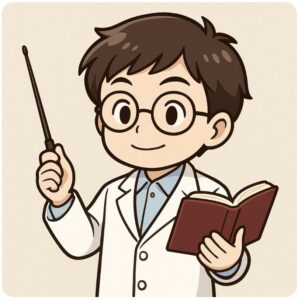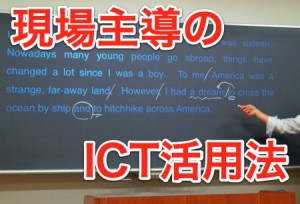AIラジオ4種類のモードで理科学習が変わる(NotebookLMでAIが「意志」を持つ時代へ?)
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「生成AIを授業でどう活用すればいいんだろう?」
先生方は、日々そう考えているのではないでしょうか。教科書の内容をAIに説明させる?プリント作成を任せる?もちろん、それだけでも便利ですが、実はもっと奥深い、生徒の思考力を引き出すような使い方が可能になっています。
AIは「意志」を持つか?NotebookLMの新機能
先日、Googleの新しいAIツール「NotebookLM」に、一つのドキュメントから複数の視点の音声コンテンツを作成する機能が追加されました。これを使って、私が書いたブログ記事を読み込ませ、4種類のラジオ(ポッドキャスト)を作ってみたんです。これが、想像をはるかに超える面白さでした。
読み込ませた記事はこちらのものです。
作成したのは以下の4種類です。
- 概要(Overview): 記事の要点を簡潔にまとめる。
- 詳細(Detailed): 記事の内容を深掘りして解説する
- 議論(Debate): 2つの異なる立場から、記事のテーマについて議論する
- 批評(Critique): 記事の改善点や課題について批評する
この4つのラジオを聴き比べると、AIがまるで「意志」を持っているかのように、それぞれ全く異なる展開を見せることに驚かされました。特に「議論」と「批評」の精度は目を見張るものがあります。
授業での具体的な活用法
このAIのポッドキャスト機能は、先生方の授業に新しい風を吹き込む力を持っています。理科の授業を例に、その活用法を考えてみましょう。
- 議論(Debate)の活用
- 理科の知識が深まるポイント: AIに「地球温暖化について、推進派と反対派の立場で議論させてください」と指示してみる。生徒は、科学的な根拠に基づいた二つの異なる意見を聴き、どちらがより説得力があるかを考えることができます。単に知識を暗記するだけでなく、多角的な視点から科学的事象を捉える力や、論理的思考力が養われます。これは、AIが「疑似的な対立構造」を簡単に作ってくれるからこそできる授業です。
- 授業への応用: 授業の冒頭でAIの議論を聞かせ、その後に「君ならどちらの意見を支持する?その理由は?」と発問することで、生徒主体のディスカッションを促すことができます。
- 批評(Critique)の活用
- 理科の知識が深まるポイント: 生徒にレポートや小論文を書かせた後、AIにその文章を読み込ませ、「科学的な観点から改善点を挙げてください」と批評させます。AIは、科学的根拠の不足や論理の飛躍などを指摘してくれるため、生徒は自らの思考の弱点に気づくことができます。これは、教師が一人ひとりの生徒のレポートに時間をかけて詳細なフィードバックをするのが難しい場合でも、質の高い学びを提供できます。
- 授業への応用: 批評機能で得たフィードバックを元に、生徒に文章を再構成させる時間を設けることで、科学的記述力や問題解決能力を鍛えることができます。
AIを「教師の相棒」に
AIは、もはや単なる作業効率化ツールではありません。AIに異なる役割(ファシリテーター、批判者、要約者など)を与え、そのアウトプットを授業で活用することで、生徒の学びは劇的に進化します。
AIは、あくまで教師の専門性を補完する「相棒」です。AIが提供する多角的な視点や鋭い批評を授業に組み込むことで、先生方の指導力はさらに高まり、生徒たちの知的好奇心はますます刺激されることでしょう。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。