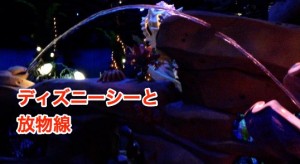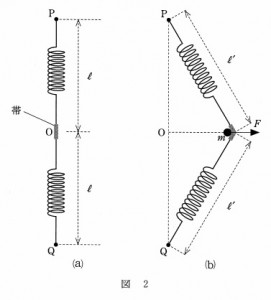タコが枕にするウニ?「タコノマクラ」「ハスノハカシパン」に隠された科学のロマン
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
「この夏休み、海に行ったときに何を見つけましたか?」
そう生徒に問いかけて、授業の導入に使える面白い題材を今回はご紹介したいと思います。
先日、筆者が海辺を歩いていると、砂浜に落ちている不思議な物体を見つけました。なんだろうと手に取ってみると、硬くて石のようです。表面には繊細な模様が描かれていて、裏側には穴が空いています。


※追記 この写真の生き物のですが、タコノマクラではなく、ハスノハカシパンであると教えていただきました。このような記事も見つけましたので、併せて紹介します。ご指摘ありがとうございました。
この不思議な物体の正体はハスノハカシパンというウニの仲間であることがわかりました。タコノマクラ目ヨウミャクカシパン科に属するそうです(wikipedia)。
ウニと聞くとトゲトゲした生き物を想像しますが、ハスノカシパンやタコノマクラは平たい形をしています。食用には向かないため、スーパーなどでは見かけません。
「タコノマクラ」という面白い名前は、その名の通り、タコが枕にしそうな形をしていることから名付けられたという説があります。しかし、実際のところは定かではありません。タコノマクラは英語で「sand dollar」と言います。これは「砂の上の1ドル銀貨」という意味で、平らで丸い形を銀貨に見立ててつけられたようです。どちらの名前もロマンがあって想像力をかき立てられますね。
ハスノカシパンは「ウニ」なのか?
ところで、ハスノカシパンやタコノマクラは本当にウニの仲間なのでしょうか。
ウニ綱に分類されるタコノマクラは、ウニと同じ棘皮動物です。ヒトデ、ナマコなどもこのグループに含まれます。タコノマクラはウニのような硬い殻を持っていますが、これは棘皮動物に共通する炭酸カルシウムの骨片でできています。この骨片が繋がって殻を形成しているのです。
この穴の空いた平たい殻は、ハスノカシパンが死んで中身がなくなった状態です。ハスノカシパンの生体は、この殻の表面に短いトゲがたくさん生えています。そして、このトゲを使って砂の中を移動したり、餌を食べたりします。
生徒にハスノカシパンやタコノマクラを見せて、これがウニの仲間だと伝えると、きっと驚きや疑問が生まれるはずです。
「なぜウニなのにトゲがないの?」「そもそもウニって何?」といった問いから、生物の分類や進化について考えるきっかけを与えることができます。
体のつくりと機能: 殻の裏側にある穴は「口」です。そこから砂の中の有機物を食べています。この構造から、生物の体のつくりが、その生活環境や食べ物に合わせてどのように適応しているのかを教えることができます。
身近な自然の不思議: 海岸で拾ったものが、実は奥深い科学の題材になることを知る良い機会です。「砂浜には、どんな不思議なものが落ちているかな?」と生徒に尋ねて、身近な自然への興味を引き出すことができます。
この夏休み、生徒たちが持ち帰った砂浜の「お土産」が、もしかしたら素晴らしい科学の教材になるかもしれません。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。