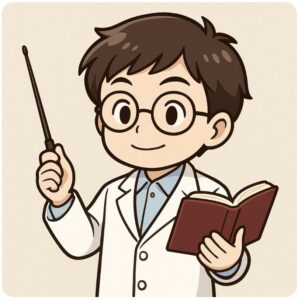「ミラバケッソ」に会いに行ったら、壊れたダチョウに遭遇!不思議な行動から考える動物の心理
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
動物園や牧場で、思わず「なんでそんなことしてるの?」と首をかしげてしまうような、動物たちの不思議な行動に出会ったことはありませんか? 今回は、そんな「ナゾ行動」の一つから、科学の面白い考え方を一緒に探求してみたいと思います。
アルパカに会いにいったら、謎のダチョウに遭遇!
数年前、私はある目的で「那須アルパカ牧場」を訪れました。その目的とは、株式会社クラレのCMで「ミラバケッソ」と鳴く(?)ことで一躍有名になった、あの愛らしいアルパカに会うことでした。のほほんとした姿を想像しながら歩いていると、私は思わぬ光景に足を止めました。
一羽のダチョウが、柵の中にある水道管を、何度も何度も、それはもう熱心にクチバシで叩き続けているのです。
一体何をしているのでしょうか? 水が出てくることを期待しているのか、ただ遊んでいるだけなのか、それともダチョウの習性に何か秘密があるのか…? この「なぜ?」を、科学の視点で少し深掘りしてみましょう。
水道管を叩き続けるダチョウ…その理由を科学的に考えてみよう!
動物の不思議な行動を解明しようとするとき、科学ではいくつかの「仮説」を立てて考えます。今回のダチョウの行動についても、いくつかの可能性が考えられます。
仮説1:ストレスサイン?「常同行動」という可能性
一つ目は、「常同行動(じょうどうこうどう)」という可能性です。これは、動物が退屈だったり、ストレスを感じたりしたときに、同じ行動を意味なく繰り返してしまうことを指します。例えば、動物園のクマが同じ場所を行ったり来たりする行動などがこれにあたります。
人間も、緊張すると貧乏ゆすりをしたり、指で机をトントンと叩いたりすることがありますよね。それと少し似ているかもしれません。このダチョウも、もしかしたら何か満たされない気持ちを、水道管を叩くことで紛らわしていたのでしょうか。
仮説2:賢い証拠?「学習」して水を求めている可能性
二つ目は、このダチョウがとても賢いという可能性です。以前、偶然クチバシが当たったときに蛇口から水が少し出てきた、という経験をしたのかもしれません。その成功体験を 「学習」 し、「ここを叩けば水が飲める!」と考えて行動を繰り返している、という説です。
カラスがクルミを道路に置いて車に割らせるように、動物たちは私たちが思う以上に賢く、経験から学ぶ能力を持っています。もしこの説が本当なら、このダチョウはなかなかの策士ですね。
仮説3:ただ楽しいだけ?「遊び」という可能性
三つ目は、もっともシンプルな理由、「遊び」です。金属製の水道管を叩いたときの「コンコン!」という音や、クチバシに伝わる振動が面白いのかもしれません。人間の子どもが、いろいろな物を叩いて音の違いを楽しむように、ダチョウも純粋な好奇心からこの行動を楽しんでいた可能性も十分に考えられます。
動物にとって「遊び」は、狩りの練習をしたり、体の使い方を学んだりするための大切な行動でもあるのです。
本当の理由は、このダチョウに聞いてみないと分かりません。でも、こうして「なぜだろう?」と考えて仮説を立てていくことこそが、科学の面白さの第一歩です。皆さんも動物園や牧場に行ったら、ぜひ動物たちの「ナゾ行動」を探してみてください。きっと、教科書には載っていない面白い発見が待っていますよ。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。