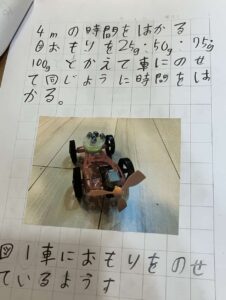タマムシはなぜピカピカに光る?国宝「玉虫厨子」に隠された科学の秘密
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
先日、学校の近くで偶然タマムシを見つけました。埼玉県で一度見たきりで、何十年かぶりの再会だったため、その驚きと美しさに思わず生徒と一緒に観察してしまいました。

この「タマムシ」という響き、どこかで聞いたことはありませんか?そう、飛鳥時代に作られた国宝「玉虫厨子(たまむしのずし)」。修学旅行の時に見つけて説明文を何度も読んでしまいました。聖徳太子にゆかりのある法隆寺にあるこの仏具には、たくさんのタマムシの翅(はね)が貼り付けられていたらしいことを、美しい光沢を見ながら思い出しました。
なぜ、タマムシはこんなにも鮮やかで、見る角度によって色が変わる金属のような輝きを放つのでしょうか?今日は、この「タマムシ」の翅に隠された科学の秘密と、意外と知られていないその一生について、皆さんと一緒に探究していきたいと思います。
なぜ、タマムシは宝石のように輝くのか?光沢の秘密は「構造色」にあった!
タマムシの翅が放つ鮮やかな光沢は、色素によるものではありません。その色の正体は、構造色(こうぞうしょく)という特別な物理現象によって生まれています。
身近な例を挙げると、シャボン玉や水に浮いた油膜、そしてCDの裏側がキラキラと虹色に光るのと同じ仕組みです。これらは、表面に当たる光が、薄い膜の内部で反射と干渉を起こすことで色を生み出しています。

タマムシの翅も同様で、表面は非常に薄い透明な膜が何層にも重なった「多層膜構造」になっています。この層は、ナノメートル(10億分の1メートル)という非常に規則正しい間隔で並んでいます。
ここに光が当たると、各層の表面で反射が起こります。それぞれの層を通過する光の距離がわずかに異なるため、反射された光の波長(色)ごとに、強め合ったり打ち消し合ったりする「光の干渉」という現象が起こります。
特定の波長の光だけが強め合って目に届くことで、鮮やかな緑色や赤色に見えるのです。見る角度によって色の見え方が微妙に変わるのは、光の進む距離が変わるためです。
この仕組みは、CDの表面にある微細な溝が光を回折させる「回折格子」と同じ原理であり、タマムシはまさに自然が作り出した「光の芸術品」と言えるでしょう。詳しくはこちらの動画も併せてご覧ください。
成虫の寿命はたった1〜2ヶ月!?タマムシの意外な一生
タマムシの生態を調べてみると、その美しい成虫の姿からは想像もつかない、驚くべき一生を送っていることが分かります。
短い成虫の寿命と食性
- 成虫のタマムシは、主にエノキやケヤキなどの葉を食べ、夏の日差しの強い時間帯に活発に飛び回ります。この美しい金属光沢は、天敵である鳥を威嚇する効果があると考えられています。
- しかし、成虫の寿命は非常に短く、わずか1〜2ヶ月ほどしかありません。その短い期間に、交尾と産卵という大切な役割を果たします。
幼虫時代は「木の中」で2〜3年
- メスはエノキやケヤキ、サクラなどの枯れ木や、弱った木のひび割れ部分に卵を産み付けます。卵から孵化した幼虫は、木の中に潜り込み、木材の内部を食べて成長します。そのため、幼虫は外からはほとんど見えません。
- 幼虫は、朽ち木の中で2〜3年という長い期間を過ごします。この間に何度も脱皮を繰り返し、十分な大きさに成長すると、蛹(さなぎ)になります。蛹から羽化して成虫になると、ようやく固い木を食い破って外の世界へ出てきます。
なぜ、今タマムシが貴重なのか?
この長く暗い幼虫期間を経るため、タマムシは幼虫の食料となる枯れ木が豊富にある環境でしか生きていけません。里山の管理不足や都市開発による生育環境の減少が、タマムシの個体数を減らす一因となっています。そのため、地域によっては絶滅危惧種に指定されているところもあります。
今回、私がタマムシを見つけた場所は、学校の近くにある大学の敷地内でした。そこには、エノキやケヤキなどの木々が生い茂り、枯れ木や弱った木も自然のまま残されているようです。このような、タマムシが生きるために必要な環境が保たれていることに、改めて身近な自然の大切さを感じました。
皆さんも、もしタマムシを見つけたら、その光沢の美しさだけでなく、彼らがたどってきた長く神秘的な一生にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。