【オームの法則】乾電池1つで電子190京個!?オームの法則で電気のナゾを解き明かせ
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
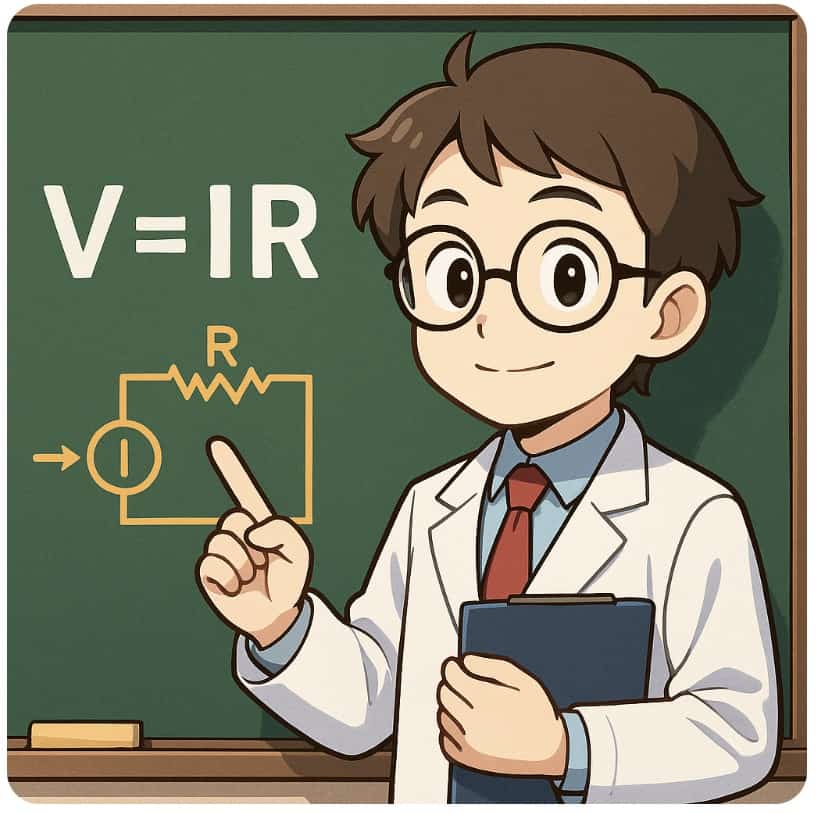
V=IR
電圧=電流×抵抗
このシンプルな数式、見覚えがある人も多いのではないでしょうか?そう、これこそが電気回路の基本中の基本、オームの法則です。左辺の「V」は電圧、右辺の「I」は電流を表し、「R」は抵抗、つまり電流の流れにくさを数値化したものです。今回は、皆さんが普段何気なく使っている電気の「流れ」、電流の正体に、このオームの法則を絡めて深く迫ってみましょう。
見えない電気の流れを追え!
私たちが電池と豆電球を導線でつなぐと、豆電球はまばゆい光を放ちます。でも、その導線をプツンと切ると、どうでしょう?豆電球の明かりは瞬時に消えてしまいます。このことから、導線の中には何かが流れているに違いない、と私たちは直感しますよね。
かつて、この不思議な現象を目の当たりにした初期の科学者たちは、電池のプラス極から「プラスの電荷」が導線の中を流れ、マイナス極に戻ってくると考えました。そして、この「プラスの電荷の流れ」こそが電流だと定義されたのです。
しかし、科学の歴史は時に驚きの真実を私たちに突きつけます。そう、この仮説は後になって「誤り」であることが判明したのです!一体、導線の中では本当に何が流れていたのでしょうか?
電流の正体は「自由電子」だった!
銅のような金属は、原子同士が金属結合という特殊な結びつき方をしています。この結合のおかげで、原子の一部である電子が、まるで高速道路を走る車のように、金属原子の間を自由に動き回れるようになります。これが、自由電子の正体です。
普段、自由電子たちは何のルールもなく、あちこちへ気ままに動き回っています。しかし、ここに電池を接続すると、金属内に電場という「電気の世界の坂道」が発生します。すると、この電場によって力を受けた自由電子たちは、まるで示し合わせたかのように、一斉に同じ方向に動き始めるのです!
ここで重要なのは、自由電子が持っている電気はマイナスだということ。電場からは逆向きの力を受ける性質があるため、マイナスの電気を持った電子は、電場とは逆の方向に動きます。そう、このマイナスの電気を持つ電子の流れこそが、電流の真の姿だったのです!
世紀の大逆転!それでも「電流の向き」が変わらないワケ
「え?電流ってプラスの電荷の流れって習ったのに、実際はマイナスの電子が逆方向に流れてるの!?」
はい、おっしゃる通り、19世紀後半にこの事実が明らかになったとき、多くの人が驚きました。しかし、ご安心ください。当時すでに「電気学」は学問として確立されており、いまさら電流の定義を変えてしまうと大混乱が生じてしまいます。そこで、科学者たちは考えました。「プラスの電荷が右に動くこと」と「同じ大きさのマイナスの電荷が左に動くこと」は、実は電気的な効果として同じであることに気づいたのです!ちょうど、電車が右に進むのと、同じスピードで地面が左に動くのを窓から見ているようなものですね。結果的に電気量の計算などは何も変わりません。

このような理由から、電流は今も昔ながらの「プラスの電荷の流れ」として定義され、使われ続けているのです。なんとも合理的な解決策だと思いませんか?ちなみに、電流の大きさは、1秒あたりに導線のある場所を通る電気量のことで、以下の式で表されます。
I = Q/t
電流 = 電気量 ÷ 時間
そして、電流の単位はA(アンペア)です。たとえば、ある導線に1Aの電流が流れているということは、その導線には1秒あたりに+1C(クーロン)の電気量が流れていることを示しています。
電圧の正体は「電気の高さ」だった!
さて、普段皆さんが使っている電池には「1.5V」などと電圧が書かれていますよね。この「V(ボルト)」とは一体何なのでしょう?
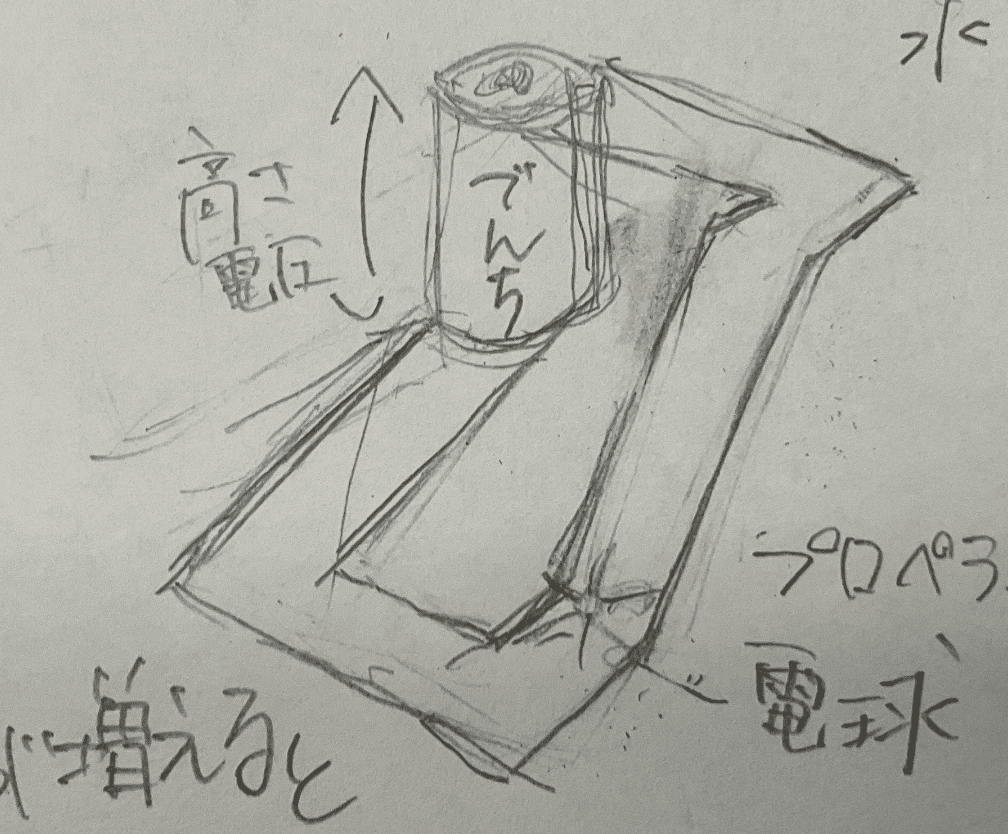
生徒がイメージとして描いたものです。
実は、電位とは電気の世界の「高さ」、つまり「静電気による位置エネルギー」のことなんです。この「電気の高さ」という視点で、電池と豆電球をつなげた電気回路をイメージしてみましょう。プラスの電荷を水分子、導線を水路と考えると、平らな水路では水は流れませんよね?これは、電池をつながずに導線だけで回路を作っても、電流が流れないことと同じです。では、電池をつなぐとどうなるのか?電池は「電気を作り出す場所」ではありません。まるで水(プラスの電荷)を低い所から高い所へと持ち上げるポンプのような役割をしているのです!
例えば、電池を通過する前の水路の高さを0Vとすると、1.5Vの電池を通過すると電荷は1.5Vの電位まで持ち上げられます。つまり、電圧とは、この2つの場所の電位の差(電位差)のことを指しているのです。1.5Vの電位まで持ち上げられたプラスの電荷は、豆電球の場所に来ると、せっかく得た位置エネルギーを使って「仕事」をします。豆電球は、まさにこの場所にある水車のようなもの。高いところから水が落ちて水車にぶつかると水車は回りますが、これと同じように、電荷が豆電球を通ると、豆電球が光るのです!
豆電球は、静電気による位置エネルギー(電気エネルギー)を熱エネルギーや光エネルギーに変える装置なんですね。そして電荷はスタート地点の0Vに戻り、また電池によって1.5Vの「高さ」を与えられ…という具合に、回路の中を延々と流れ続けます。もし電池の電圧が3Vや4Vと大きければ、その分高い場所まで電荷が運ばれるので、豆電球はより明るく光るわけです。
ぶつかり稽古で光る豆電球!
では、豆電球の中では具体的に何が起こっているのでしょう?
導線の中を流れる自由電子たちは、実はスーッと滑らかに動いているわけではありません。まるでピンボールのように、導線や豆電球を構成する原子核に 「ゴン!」「ガン!」 と激しく衝突しながら進んでいます。
衝突した電子は、その運動エネルギーを原子核に分け与えます。運動エネルギーをもらった原子核は激しく振動を始め、この振動がやがて熱エネルギーや光エネルギーとして私たちに届くのです。これが、豆電球が光るメカニズム!電子たちの「ぶつかり稽古」の成果なんですね。
抵抗は電流の「交通整理」
もし1本の水路にたくさんの水車が並んでいたら、水の流れは悪くなりますよね?水車は水の流れを妨げていることになります。
これと同じように、電気回路でも豆電球をたくさん直列につなげると、豆電球一つ一つの明るさは暗くなり、全体として電流は流れにくくなります。豆電球のように電気エネルギーを使う部品は、回路の電流の流れを妨げる役割をするのです。このように電流を流れにくくするものを抵抗といい、その「流れにくさの量」を抵抗値と呼び、単位はΩ(オーム)を使います。
オームの法則、いざ実践!
さあ、いよいよ本丸、オームの法則です。
回路に大きな電圧Vを与えれば、当然流れる電流Iは大きくなります。これは、蛇口をたくさん回せば(電圧を大きくするに相当)、勢いよく水が流れる(電流が流れる)のと同じ。逆に、抵抗値Rが大きな抵抗をつけると、これはホースを踏んでいる強さにあたりますが、回路に流れる電流Iは小さくなります。

つまり、電流Iは電圧Vに比例し、抵抗Rに反比例するという関係があります。
I = V/R
そして、この式を電圧Vについて整理すると、皆さんもよくご存じの、あの形になるのです!
V = I R
電圧 = 電流 × 抵抗値
これが、電気回路のあらゆる計算の基礎となる、オームの法則の公式です。
乾電池1つで、一体何粒の電子が流れている?
では、実際にオームの法則を使って、私たちの身近な例を計算してみましょう。小学校の理科で使った、電圧1.5Vの乾電池1つで豆電球を光らせた場合を考えてみましょう。この豆電球の抵抗値は、1.5Vの電圧がかかったときに5Ωだったとします。
オームの法則を使えば、回路を流れる電流はすぐに計算できますね。
I = 1.5 [V] / 5 [Ω] = 0.3 [A]
つまり、この回路には0.3Aの電流が流れていることがわかりました。次に、この0.3Aという電流が、1秒間にどれくらいの電気量を運んでいるのか、先ほどの電流の式(I = Q/t)を使って逆算してみましょう。
Q = 0.3 [A] × 1 [s] = 0.3 [C]
はい、1秒間に0.3クーロンの電気量が抵抗を通っていることがわかりました。ここで豆知識です。電子1つが持っている電気量の大きさは、なんと 1.6 × 10^-19 クーロン ということが知られています。このとてつもなく小さな電気量を持つ電子が、一体どれだけ流れているのか?計算してみると…
0.3 [C] ÷ (1.6 × 10^-19 [C/個]) ≈ 1.9 × 10^18 個
なんと、乾電池1個で豆電球を光らせているとき、1秒間に10の18乗個もの電子が抵抗の中を通過していたのです!まさに「京」の単位に近い数です。目には見えないけれど、電気の世界ではとんでもない数の電子たちが、せっせと働いているんですね。
オームの法則は、ただの数式ではありません。目に見えない電気の世界で、電圧が電子を押し動かし、抵抗がその流れを妨げ、結果として電流が生まれるという壮大なドラマを解き明かすカギなのです。この知識があれば、身の回りの電気製品がどうやって動いているのか、その裏にある科学の不思議がもっと面白く感じられるはずですよ!
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。


