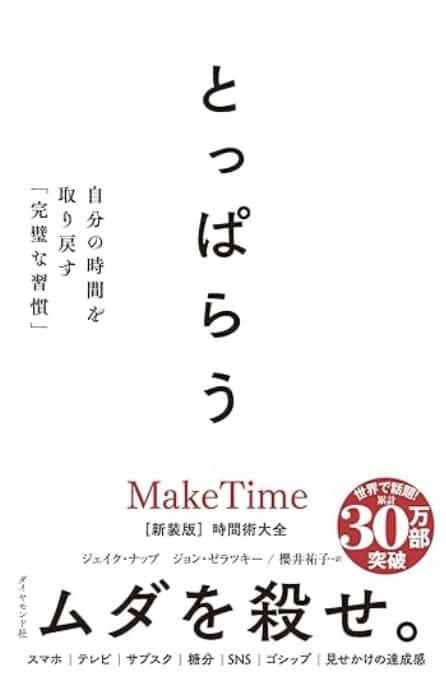世界がアナログ回帰する理由とは? タブレット教育の落とし穴
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
今回は、理科の話題ではないのですが、多くの学校で導入されているデジタル端末、特にタブレットの活用方法について、少し立ち止まって考えてみたいと思います。先日、ある記事を読んで、私自身も深く共感することがありました。それは、「デジタル教育は本当に子どもたちの学力を向上させているのだろうか?」という問いです。
文部科学省の「GIGAスクール構想」により、全国の小中学校で「1人1台端末」が実現し、タブレットを活用した授業が当たり前になりました。しかし、私が授業でクロームブックを生徒に自由に使わせると、どうしても授業と関係ないことに意識が向いてしまう生徒がいるのも事実です。これは、生徒が子供だから、意思の力が弱いからからというわけでは決してありません。大人である私たちが、スマートフォンの誘惑に勝てないのと同じではないでしょうか。ちょっとした隙間時間にも、スマホを見てしまったりしていませんか?仕事中でもです。これはアプリ開発者が一生懸命良かれと思って、決して悪意はなく、たくさんの人にもっと使ってもらいたいといったことを考えて、開発されているので逃れることはできません。
最近、海外の教育現場では、タブレット教育から再び紙の教科書やノートに戻る動きが加速しているという記事を読みました。この記事が指摘しているデジタル教育のデメリットは、私たち現場の教師が肌で感じていることと重なる部分が多く、非常に考えさせられました。こちらの記事をご覧ください。
「タブレット」は子どもの学力を下げる…世界の教育現場がデジタルからアナログへ回帰中
デジタル教育のデメリットと向き合う
- 学力と読解力の低下:
国際調査では、デジタル教材に頼ることで深い読解力が育ちにくく、集中力も低下する傾向が報告されています。画面上の文章は、記憶への定着が浅いという研究結果もあるそうです。 - 子どもの健康リスク:
長時間画面を見続けることによる視力低下、目の疲れ、姿勢の悪化、そしてブルーライトが原因となる睡眠障害も懸念されています。 - 教員の負担と格差:
ICT教育には専門的な知識が必要ですが、十分な研修が行き届かないまま導入されたため、教師によって指導方法にばらつきが生じ、本来の教育に集中できないという声も上がっています。
この指摘を読んで、私は「なるほど」と深く納得しました。私自身も、仕事中にパソコンが発する通知に集中力を妨げられることがしばしばあります。たった数秒の通知でも、そこから意識を授業に戻すには、かなりのエネルギーが必要になります。
この問題意識から、私は自分の生活でもデジタルとの付き合い方を見直すようになりました。スマートフォンの通知をすべて切り、SNSアプリをアンインストールしたり、アクセスしにくい場所に移動させたりしました。すると、どうでしょう。スマホを触る時間が激減し、目の前の仕事や読書に集中できるようになったのです。これは『とっぱらう』という本で紹介されていた方法で、非常に効果がありました。
デジタルとアナログの最適なバランスを見つける
この記事でも結論づけられていますが、タブレットはあくまで「学習手段の一つ」であり、すべてを代替するものではありません。動画やグラフで視覚的に理解を深める、実験データを即座に共有するといったデジタルならではの利点は大いに活用すべきです。
大切なのは、「いつ、どのように使うか」を明確にすること。生徒にタブレットを自由に使わせるのではなく、使う場面と使わない場面をしっかりと区別し、メリハリのある授業をデザインすることが求められています。アナログとデジタルの良さをバランス良く組み合わせることで、生徒たちの学びはもっと深まるはずです。この機会にデジタルツールとの付き合い方を見直してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!