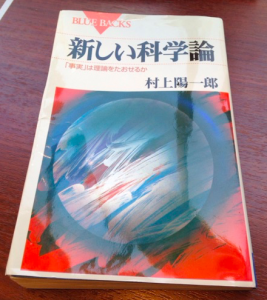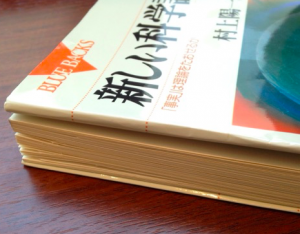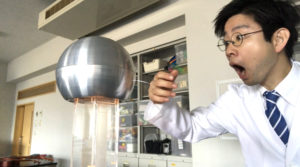科学は進歩しない!?『新しい科学論』が突きつける
サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。
「新しい科学論」―科学の見方がガラリと変わる1冊!
今回は、村上陽一郎先生の 『新しい科学論 ~「事実」は理論をたおせるか~』 を読んだので、その衝撃をみなさんにシェアしたいと思います。
amazon:新しい科学論 ~「事実」は理論をたおせるか~
この本、1979年に初版が出て、49刷以上!科学書としてはモンスター級のロングセラーなので、ご存じの方も多いかもしれません。
「新しい」って、むしろ古い?
タイトルに「新しい」とついていますが、最初に出たのは1979年。「え、全然新しくないじゃん?」と思うかもしれません。でも、この本はそんな単純な話ではありません。むしろ、今読んでも衝撃的で、科学に対する考え方が根本からひっくり返る可能性があります。自分の中の科学の捉え方が変わりました。
「事実」は理論をたおせるか?
本書のサブタイトル 「事実」は理論をたおせるか 。なんとも挑戦的な問いですよね。これは、
「古い理論があったとき、新しい事実(データ)が集まれば、その理論は倒されるのか?」
という問いかけです。
「そりゃ、倒れるでしょ?」
「だって、科学は進歩するものじゃん?」
そう思いますよね。ケプラーの惑星の法則の発見とか、いろんな科学の歴史を見れば、事実によって古い理論が覆された例はたくさんあります。でも、本書では 「必ずしもそうとは限らない」 と述べられています。えっ、どういうこと!?
ニュートン力学と相対性理論の関係
たとえば、ニュートン力学(古典力学)は、相対性理論の発見によって「内包」されました。つまり、完全に否定されたわけではなく、より広い理論の一部として組み込まれたんですね。ここで本書は驚きの主張をします。
「内包されたニュートン力学と、内包される前のニュートン力学は別物である」
「え? いや、同じでしょ?」
そう思うかもしれません。でも、本書を読めば、「あ、これは確かに別物だ…!」と納得するはずです。これは、科学の理論が社会通念や文化と切り離せないほど密接に関係していることとも関係があります。
科学は「進歩」しない!?
「科学の進歩」という言葉をよく耳にしますが、本書では、科学は「進歩する」ものではなく、「革命」によって変わっていくと述べられています。つまり、少しずつ積み重ねて前進していくのではなく、ある時点でガラリと変わる瞬間があるということです。まさに、パラダイムシフトですね。
客観的事実って、本当に客観的?
これも驚きのポイント。本書では、「客観的事実」というものは、すべての人にとっての客観的事実ではありえないと指摘しています。つまり、
「ある特定のコミュニティー」にとっての客観的事実があるだけ。
しかも、その客観的事実にはレベルがある。「え、でもそれって科学として大丈夫なの?」と思うかもしれませんが、「それはそれで良い」というのが本書のスタンスなんです。
読まなきゃ損!
この本には、まだまだ驚くべきことがたくさん書かれています。そして最後には、村上先生からの 「私たちは科学とどう向き合うべきか」 という問いが投げかけられます。特に印象的なのが、 「もし必要ならば…。」 という最後の言葉。ここに込められた意味を考えると、ますます深く考えさせられます。正直、この紹介文だけでは本書の魅力を全部伝えきれません。
むしろ、読めば読むほど「うわぁ、これはすごい…」と感じるはず。
理系・文系問わず、絶対に読むべき1冊です。ぜひ、手に取ってみてください!
科学のタネを発信中!
2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!
- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20
 体中に梱包材をはりつけてみよう!
体中に梱包材をはりつけてみよう!
テレビ番組等・科学監修等のお知らせ
- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。
書籍のお知らせ
- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。
- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ
- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師
- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20
- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。
- 10/10(土) サイエンスショー予定
- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。