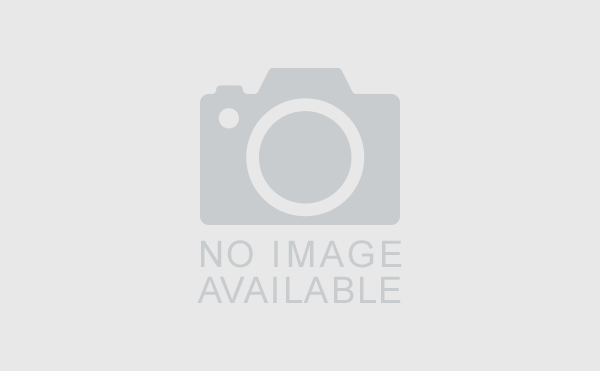童話「ウサギとカメ」を題材にしてv-tグラフとx-tグラフを考えてみよう!
サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
誰もが子供の頃に聞いたことのある童話、「ウサギとカメ」。 足の速いウサギと、ゆっくり進むカメが競走をするお話ですが、この物語を「理科の視点」から読み解くと、運動の法則を理解するのにとても優れた教材になることをご存知でしょうか?今回は、この有名なレースを2種類のグラフを使って分析してみるということを考えてみましょう。物語の裏側に隠された科学的な面白さが見えてきますよ。
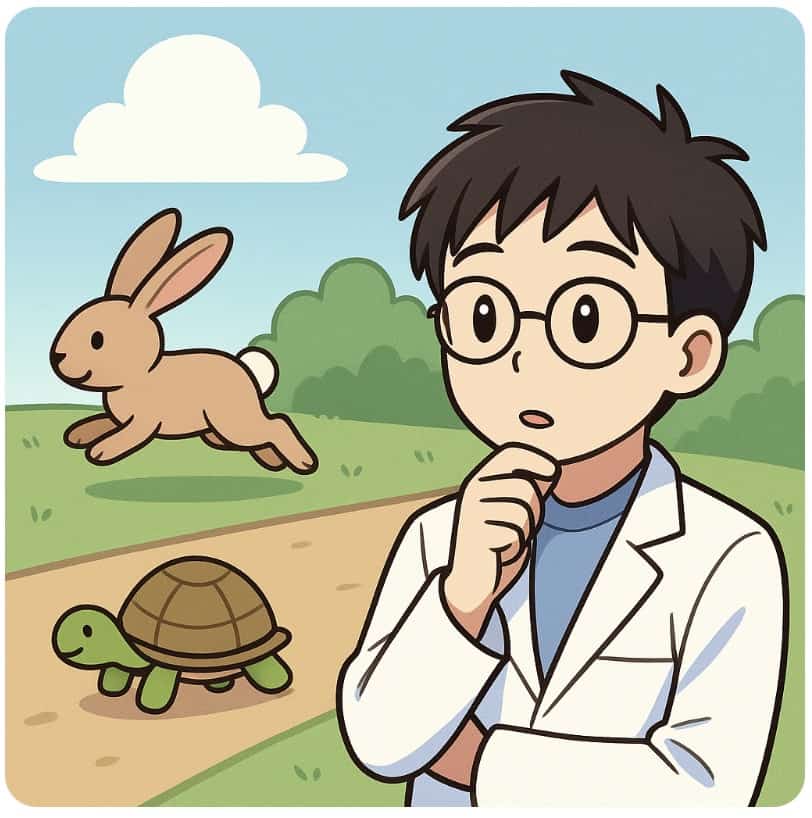
運動の様子をグラフで「見える化」してみよう
物体の動きを理解するためには、言葉で説明するよりもグラフにするのが一番です。特に物理の世界では、動きを以下の2つのグラフで表すことがよくあります。
時間とともに「位置」がどう変わったかを表すグラフ(x-tグラフ)
時間とともに「速さ」がどう変わったかを表すグラフ(v-tグラフ)
では、ウサギとカメのレースをグラフにすると、どのような形になるのでしょうか?ぜひ描いて考えてみてください。
ウサギのグラフは、スタート直後にグンと速さが上がり、途中で居眠りをして速さがゼロになり、最後に慌ててまた速くなる、という変化の激しい形になります。 一方、カメのグラフは、最初から最後まで速さが変わらない、低くて平らな一本線になります。性格が全く違う2匹の動きが、グラフの形にもはっきりと表れていますね。
「面積」に隠された秘密
ここで、少し発展的な視点を持ってみましょう。実は、このグラフには面白い数学的な性質が隠されています。「速さ」と「時間」のグラフ(v-tグラフ)において、グラフの線と横軸で囲まれた部分の「面積」は、その物体の「移動距離」を表しているのです。
このあたりもグラフ作成のヒントになりますよ!
一見すると全く違う形をしているウサギのグラフとカメのグラフですが、厳密にゴールに到着するまでの間を考えると、両者のグラフの面積(移動距離)は同じになります。なぜなら、ウサギもカメも、スタートからゴールまで同じ距離を走った(あるいは歩いた)からです。
物語を科学する面白さ
「形は違うけれど、面積は同じ」。 これは、どんなに速く走っても、途中で止まってしまえば、コツコツ進む相手と同じ距離しか進めないということを、数学的に証明しているとも言えます。このように、身近なストーリーをグラフに置き換えて考えてみると、ただの昔話が「速度の合成」や「積分(面積計算)」の入り口に見えてきませんか? ぜひ、他の物語や日常の動きもグラフにして、その背後にある法則を探ってみてください。
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら
・運営者の桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!
![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!
科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!