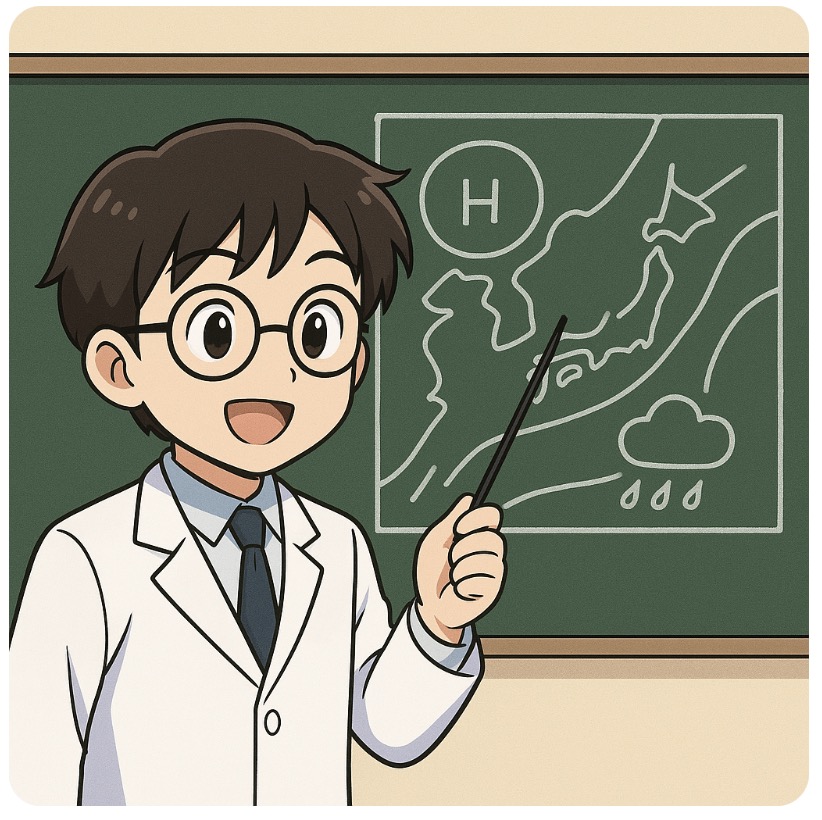サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。
気象通報を聞きながら、地図に天気図記号を書いていく。そんな授業を私も受けたことがあります。ラジオから流れる独特の読み上げを聞き、一つひとつの記号を紙の上に書き込んでいくあの作業は、デジタルな情報があふれる今、かえって新鮮に感じるかもしれません。
データとして完成された天気図を見るだけでは得られない、
「なぜこの記号はここに書かれているのか?」
「風向と風速はどう関係しているのか?」
といった疑問が自然と湧き、生徒が自ら気象の様子を読み解く力が養われます。
しかし、今はもうラジオで気象通報は流れてきません。あの生きた授業を今の生徒たちに体験させてあげたい…そう思っている先生も多いのではないでしょうか?ご安心ください。実は、あの放送を聴きながら天気図を作成する体験を再現できる、素晴らしい教材がインターネット上に存在します。今回は、その活用方法を具体的にご紹介し、生徒たちの理科への関心を劇的に高める授業を一緒に創り上げていきましょう。
準備はたったこれだけ!
この授業を実践するために必要なのは、以下のシンプルなアイテムだけです。
PCまたはタブレット(スピーカー付き)
専用の記録用紙(印刷したもの)
筆記用具(鉛筆、色鉛筆、ペンなど)
定規
活用するウェブサイトと動画
この授業の鍵となるのが、以下のウェブサイトとYouTubeチャンネルです。
気象通報【毎日読み上げ】 というチャンネルです。
https://www.youtube.com/@user-yp5tg3hb4o
毎日更新されているので、定期的な授業の練習にもぴったりですね。答えも毎回出してくれるので、生徒自身が振り返り学習をするのにも役立ちます。専用の記録用紙は以下のサイトからダウンロードできます。
また、気象庁の読み上げ原稿はこちらです。
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/gyogyou/index.html
パソコンの画面読み上げ機能で読ませても良いですね。
授業での具体的な手順(30〜45分)
導入(5分):
まず、完成した天気図を提示し、生徒に記号の意味を軽く復習させます。
「これらの記号が、今から読み上げられる情報だけで、この白地図に書き込めるか挑戦してみよう!」と生徒の意欲を刺激します。
実践(15〜20分):
YouTubeの動画を再生し、生徒は各自、用紙に天気図記号を書き込んでいきます。
最初は少し戸惑う生徒もいるかもしれませんが、それが「リアルな」学びの体験です。途中で動画を一時停止したり、繰り返し聞かせたりすることも可能です。
気圧や風向、風速、天気など、バラバラな情報が少しずつ図に書き込まれていくにつれて、気象の全体像が浮かび上がってくる感覚を味わわせます。
振り返りと解説(10〜15分):
動画の解説や、提供されている答えの画像を使い、生徒が書いた天気図と見比べながら答え合わせをします。
なぜこの地点は曇りなのか?(例:低気圧の前面にあるから)、風向と風速が急に変わっているのはなぜか?(例:前線が通過したから)など、記号の背後にある気象現象を問いかけ、理科の知識と結びつけさせます。
生徒同士で自分の書いた図を見せ合い、学びを共有する時間を設けると、より効果的です。
この授業は、生徒が**「気象予報士」**になったような気分で、データから情報を読み解き、自分で天気図を完成させる楽しさを体験できる点が最大のメリットです。完成された天気図をただ眺めるだけでなく、その作成過程に触れることで、生徒たちは天気図記号一つひとつの意味を深く理解し、気象学への興味を育むことができるでしょう。
この記事のキャッチーなタイトル候補
【先生必見】昔ながらの天気図作成で、生徒の理科の授業が劇的変化!
座学だけじゃもったいない!天気図を「書く」体験が、深い学びを生む
天気予報の裏側を探ろう!生徒が夢中になるアクティブラーニング授業
タブレット片手に気象予報士に!手軽にできる、ワクワク理科授業プラン
お問い合わせ・ご依頼について
科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!
・運営者・桑子研についてはこちら
・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら
・記事の更新情報はXで配信中!